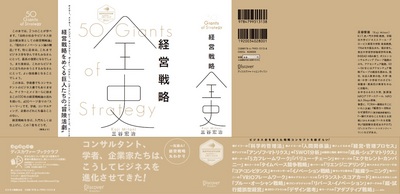ほとんどの本は、高校の授業のどこかで聞いたことあるものだと思います。
それだけこれらの本の法律・政治学への影響は大きかったと言えます。
これから(その5)まで記事にするつもりなので、お楽しみに。
1. プラトン「法律」




対話の舞台は地中海クレテ島。ゼウスの社への参詣の道すがら、「アテナイからの客人」ら三人が国制と法律について論じる。最善の国家についての理念を提示した『国家』に対し、本書では「現実にあるべき国家」の具体的な法律・制度全般について自由で大胆な提案を行う。プラトン最晩年の著作で、最大の長篇。(「BOOK]データベースより)
<レビュー>
プラトン終生のテーマであるところの、魂の不死とか、真の知識とか、正しい生き方がいちばん幸せとか、一と多の関係とか、お馴染みの議論がいつものように展開される一方で、この本でしか見られない具体的な教育論とか法律論も盛りだくさん。
(From: 眼鏡文化史研究所)
本書では、表題が示すとおり、具体的な法律制度全般を取り上げつつ、理想的国家が見出される。
すでに『国家』の中で、哲人政治は究極的なユートピアであって、「この地上のどこにも存在しない国」と言及されているが、それに次ぐ国家となるためには、正しい法律が整備されなければならない。こうした考えを背景に、本書では法律と徳との関係、法律(ノモス)が自然(ピュシス)よりまさること、そして法律の起源である神の存在等が説かれる。
(From: Amazonレビュー)
2. キケロ「義務について」


<レビュー>
3. モンテスキュー「法の精神」






法・政治思想史上の大古典として著名なモンテスキュー(1689‐1755)の『法の精神』(1748)は、三権分立論で有名であるが、近年では、法社会学、比較法学、法学史の先駆的業績として注目を沿び、法と社会の多角的な分析にさらには、異文化間の相互理解に貴重な示唆を与える書として高い評価をえている。上巻には第一・二部を収録。(全3冊)
(「BOOK」データベースより)
<レビュー>
1. プラトン「法律」


対話の舞台は地中海クレテ島。ゼウスの社への参詣の道すがら、「アテナイからの客人」ら三人が国制と法律について論じる。最善の国家についての理念を提示した『国家』に対し、本書では「現実にあるべき国家」の具体的な法律・制度全般について自由で大胆な提案を行う。プラトン最晩年の著作で、最大の長篇。(「BOOK]データベースより)
<レビュー>
プラトン終生のテーマであるところの、魂の不死とか、真の知識とか、正しい生き方がいちばん幸せとか、一と多の関係とか、お馴染みの議論がいつものように展開される一方で、この本でしか見られない具体的な教育論とか法律論も盛りだくさん。
(From: 眼鏡文化史研究所)
本書では、表題が示すとおり、具体的な法律制度全般を取り上げつつ、理想的国家が見出される。
すでに『国家』の中で、哲人政治は究極的なユートピアであって、「この地上のどこにも存在しない国」と言及されているが、それに次ぐ国家となるためには、正しい法律が整備されなければならない。こうした考えを背景に、本書では法律と徳との関係、法律(ノモス)が自然(ピュシス)よりまさること、そして法律の起源である神の存在等が説かれる。
(From: Amazonレビュー)
2. キケロ「義務について」

共和制を守るために戦った古代ローマ第一の学者にして政治家,弁論家キケロの代表作.ここにいう義務とは,人間として,また市民としての道徳的任務の完遂を意味する.キケロによれば,この義務は,国家(共和制),近親,自己の利益に対して果たされるべきものという.本書は,人生の指針として今日なお示唆するところが多い. (岩波書店ブックサーチャーより)
<レビュー>
何をしなければならないかという事より、いかに生きるべきか、何を優先させて考えるべきかを説いています。キケロは、ギリシア哲学の各学派の主張や、ローマの政治家(故人も現役も)の例を引き合いに出しながら、人間としてより望ましい、より立派な生き方を提唱します。哲学的で抽象的な思考にとどまらず、日々の生活で遭遇するような実際的な例も多く含まれます(From: Amazonレビュー)
「恩を受けた人は、その恩を心をにとめておかなければならない。しかし、恩を与えた人は、それを覚えているべきではない。」「感謝の心は最大の美徳のみならずあらゆる他の美徳の両親なり。「誰でもまちがいをすることはある。しかし、まちがいを個室するのは馬鹿以外にはない。」「生きるとは考えるということである。」「最も正しき戦争よりも、最も不正なる平和を取らん。」(From: 本書より)



法・政治思想史上の大古典として著名なモンテスキュー(1689‐1755)の『法の精神』(1748)は、三権分立論で有名であるが、近年では、法社会学、比較法学、法学史の先駆的業績として注目を沿び、法と社会の多角的な分析にさらには、異文化間の相互理解に貴重な示唆を与える書として高い評価をえている。上巻には第一・二部を収録。(全3冊)
(「BOOK」データベースより)
<レビュー>
本書は三権分立を説いた古典として有名だが、「法の精神」というタイトルから想像されるほどには、法についての理論的考察に重きが置かれているわけではない。法とは「事物の本性に由来する必然的な諸関係である」とされ、実定法に先立つ自然法の存在が承認されるが、ここでの事物の本性とは固有の風土と歴史を持った社会の本性であり、凡ゆる社会に妥当する超歴史的・普遍的なものではない。(From: Amazonレビュー)
モンテスキューの三権分立論は近代立憲主義の重要な構成要素とみられているが、モンテスキューが企図したのは、封建貴族がその裁判権を通じて絶対王政の恣意的な権力行使を抑制することであり、近代的中央集権国家のプロトタイプである絶対王政に旧勢力である貴族階級を対置するものだ。啓蒙主義のチャンピオンと目されるモンテスキューも、その限りにおいて明確に「反近代」であった。本巻ではフランス封建法の起源と変遷を辿りながら、社会的勢力としての貴族階級の興隆と衰退を、その裁判権を軸に論じていく。(From: Amazonレビュー)